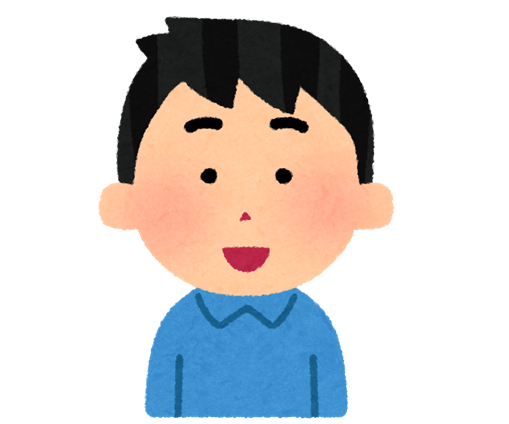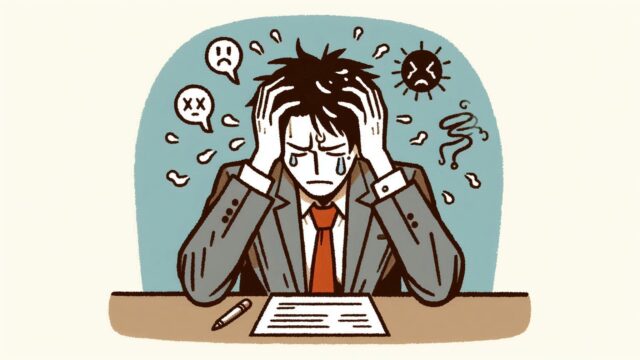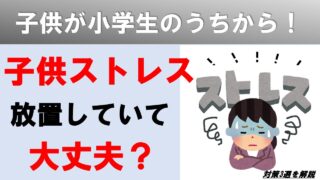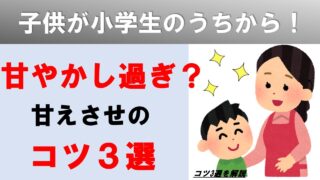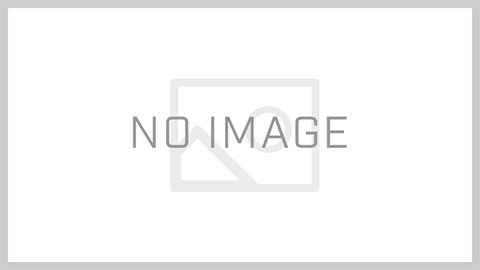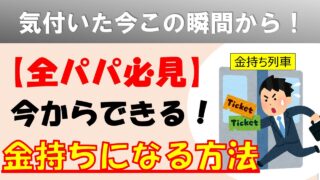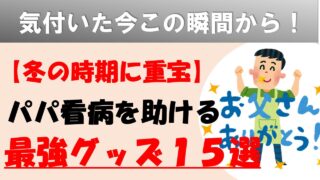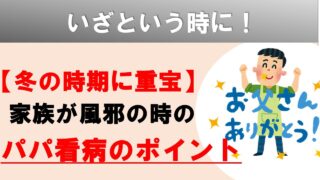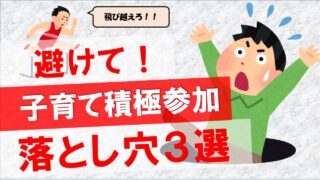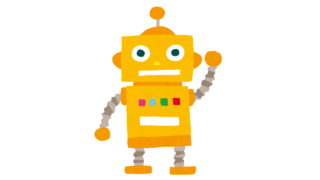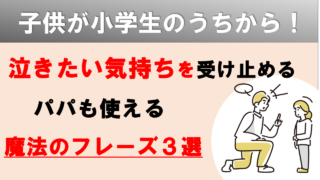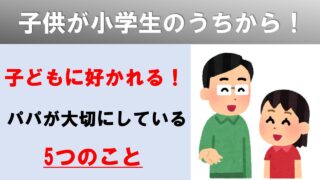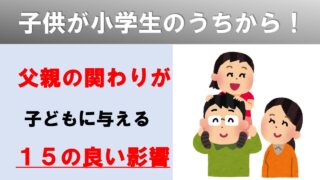こんにちは!はらきです。
リアルな子育て体験から得た、好かれるパパになるための実践ノウハウを情報発信しています。
『なんでこれをしないといけないの?』親なら絶対聞いたことがあるこの質問。
答え方に困っている方は多いんじゃないでしょうか?
なんで?なんでこうなるの?
どうして○○しないといけないの?
これはね~~。
[心の声]ああ、またこれか?!いい加減にしてくれ。。
『ああ、またか…』とため息が出そうになりますよね。
でも実は、この“なぜ攻撃”は、子どもの好奇心や思考力が育っている証拠。
親の返し方次第で、子どもの考える力はぐんぐん伸びる可能性があるんです!
「めんどくさいから適当に答えちゃう」「怒ってしまう」
そんな対応を続けると、せっかくの学びのチャンスを逃してしまうかもしれません。
今日は、家庭でできる『なぜ攻撃への上手な返し方』をご紹介していきます!
ぜひ最後までご読んで行ってね!
そんなこと言って、難しい方法なんでしょ?
そんなことないよ!
【今日からできる!】をテーマに、
今すぐできることに限定して紹介するよ!
『なぜ』を蔑ろにすべきではない理由

子どもは3〜12歳くらいの間に、好奇心と論理的思考力がぐんと伸びる時期。
この時期に親が「質問に付き合う」「考える時間を作る」ことで、将来の学力だけでなく問題解決力や創造力にも影響があることが研究でも示されています。
例えば、2010年以降の教育心理学の研究では、家庭での会話の質が子どもの論理的思考力に直結することが報告されています。
逆に、「すぐ答えを与える」「話を遮る」などの対応は、好奇心を抑えてしまい、思考力の成長を妨げる可能性があるんです。
子どもへの上手な返し方3選
子供への上手な返し方を3つ紹介します。
- 「一緒に考える」姿勢を見せる
- 「実験してみよう!」で体験学習にしてみる
- 「知らないときは一緒に調べる
次のページから詳しく解説していくよ!
① 「一緒に考える」姿勢を見せる
子どもが質問したときに、「どう思う?」と逆に問い返してみよう。
その時は自分も考えること!
親が一緒に考える姿勢を見せることで、子どもは自分で考えるプロセスを学びます。
正解よりも「考える楽しさ」が大切です。
例:
なんで空は青いの?
うーん、どう思う?光のことかな?
② 「実験してみよう!」で体験学習に
単純に答えを教えるのではなく、実験や観察で答えを見つける方法もおすすめ。
例:
子どもが質問したときに、「どう思う?」と逆に問い返してみよう。
体験することで、理解が深まるだけでなく、好奇心も育つんです。
例:
どうして氷は水になるの?
じゃあ、氷を持って温めたらどうなるか、一緒に見てみようか!
③ 「知らないときは一緒に調べる」
答えを教えるのではなく、一緒に考えよう!
もし答えが分からない時は、調べることで、調査力や情報の整理力も身につきます。
また、親は全ての情報を知っている必要はないんです。
「調べることは楽しい」と学ぶと、自主的な学びの習慣にもつながります。
恐竜はどうして絶滅したの?
わかんない。
じゃあ、パパと一緒にネットや本で一緒に調べてみよう!
おすすめ教材でさらにサポート
下記の2つを紹介します。
- 12歳までに知っておきたい論理的思考力図鑑
- レゴ(LEGO) クラシック 黄色のアイデアボックス
1.12歳までに知っておきたい論理的思考力図鑑
1つ目は。12歳までに知っておきたい論理的思考力図鑑です。
質問力や考える力を育てる家庭用の図鑑になります。
親子で一緒に読みながら、「なぜ?」の答えを探す遊びができる。
2.レゴ(LEGO) クラシック 黄色のアイデアボックス
【みんな大好き】レゴです。
レゴのブロックを見ながら。協力してモノを作ってみるGOODです。
まとめ
子どもの「なぜ?」攻撃は、面倒に感じるかもしれません。
しかし、思考力を育てる黄金チャンスなんです。
今日紹介したのはこの3選になります。
- 「一緒に考える」姿勢を見せる
- 「実験してみよう!」で体験学習にしてみる
- 「知らないときは一緒に調べる
この3つの方法を取り入れるだけで、子どもの考える力や好奇心は確実に育ちます。
親も一緒に楽しみながら、「考えることは楽しい!」という文化を家庭に作ってみてください。
後で振り返ったとき、「あの質問攻撃があったから今の思考力があるんだ」と思えるはずです。
おわりに
今回の投稿は以上になります。
ここまで読んでくれて本当にありがとう!☺
このブログでは、子供を持つ方に役立つ情報を分かりやすくまとめて配信しています。
ご意見やご質問などありましたら、お問合せページからお気軽に問合せください。
取り上げてほしいテーマや応援メッセージもお待ちしております(^^)
メッセージ頂ければ記事更新のモチベになりますのでよろしくお願いします!
現在、17:00に毎日更新をがんばっています。よろしくです!
では、また次回お会いしましょう。またね!